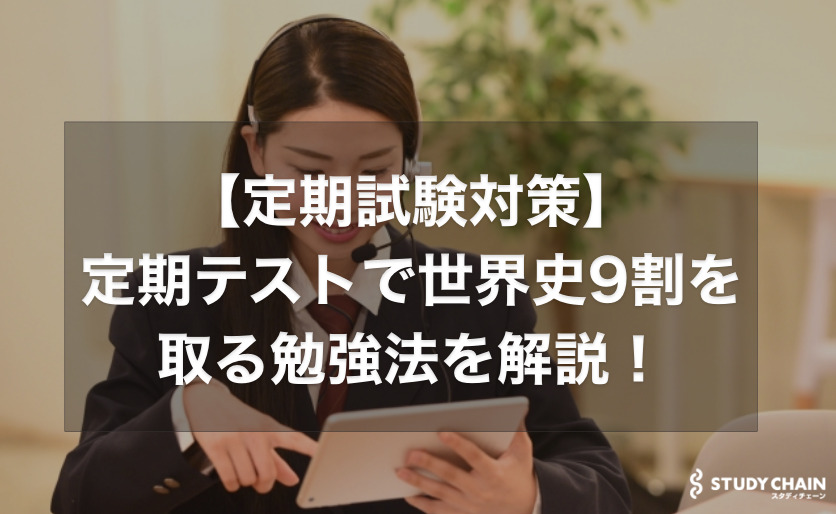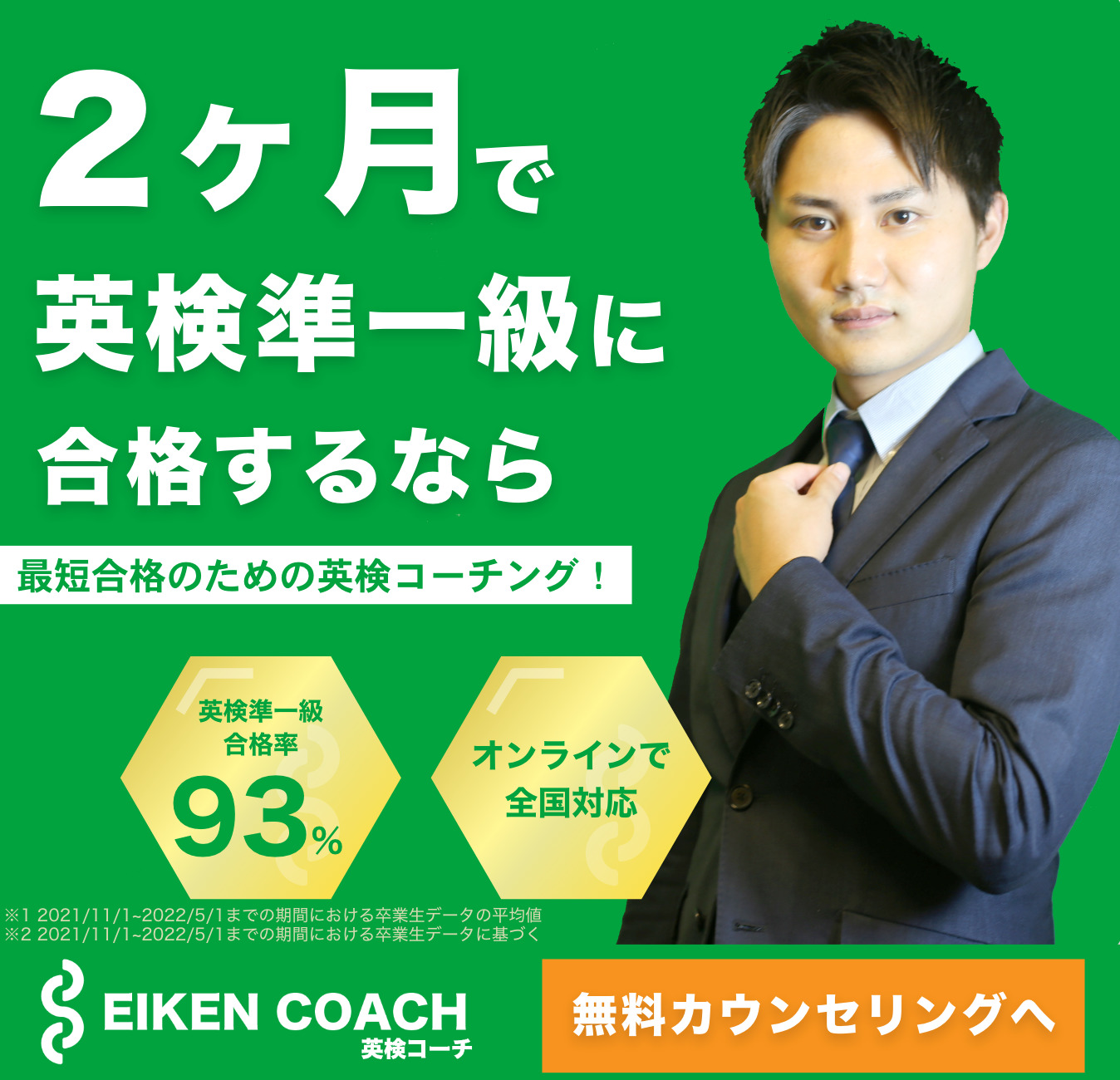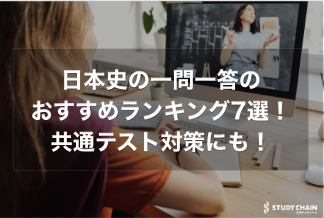世界史の定期テストの勉強法を解説します。高得点を取るためのインプットとアウトプットの方法やノートの使い方で9割取れる勉強法を徹底解説します。さらに、前日の一夜漬けの勉強法のコツや記述対策や受験勉強につながる世界史の定期テストの勉強法を難関大講師が解説します。
- 「世界史の定期テスト範囲はとても多いし、覚える必要のある用語が多すぎる…。」
- 世界史の定期テストの勉強法がわからなくて不安。あれこれ手を出して結局習得できていないことが多いです。」
- 「世界史は興味持てないし全然進めることができない。定期テストの世界史の勉強はやりたくない..。」
定期テストの世界史に対してこのような悩みを抱えている高校生も多いのではないでしょうか。そこで、今回は世界史の定期テスト、定期試験で9割以上の高得点を取る方法をご紹介します。
Contents
定期テストの世界史で高得点を狙うための勉強法<スケジュール編>

高校の世界史の授業では、授業スピードが速く、深い知識が求められます。そのため、自己流の勉強法だと定期テスト対策がうまくいかないこともあります。今回は、世界史の定期テストで高得点を取るために効果的な勉強法を紹介していきます。
世界史の定期テストの勉強は3週間前からやるのが大切
世界史の定期テストの勉強法として一番いいのは、3週間前までに始めるのが効果的です。定期テスト対策としてやるべきことを考えると少なくとも2〜3週間は必要です。世界史以外の教科の定期テスト対策は二週間以内の開始で大丈夫ですが、世界史は暗記量が圧倒的に多いので3週間前から始めるようにしてください。
実際に中間テスト、期末テストなどの世界史の定期テストで確実に高得点をとる成績のいい人の多くは、世界史の定期テストの勉強に3週間かけています。
ただ、部活動が休みになるのは定期テストの1週間前や、なかには3日だけという部活もあるでしょう。
学校の部活や課外活動が忙しいという人は定期テストの勉強と部活動の期間が重なってしまうことになりますが、今回紹介する効率的な世界史の定期テストの勉強法を取り入れると必ず結果は変わると思います。
世界史の定期テストは1週間前までに6〜7割取れる実力をつけよう
世界史の定期テストの勉強において立てるべき目標は本番で9割取りたいのではなく、1週間前までに6〜7割取れるようになるということです。
その理由としては、世界史の定期テストにおける6割はどういうことかと言うととにかく世界史の教科書の太字レベルを確実に覚えるということです。つまり、色々なことに手を出しのではなく、まずは学校の先生が作ったプリントと教科書の太字に集中して定期テストの1週間前までにやり込むことが大切です。
また、世界史の勉強に限らずのアドバイスですが、定期テスト2〜1週間前は友人もテスト勉強をしていて、世界史の先生も忙しくなるのでわからない問題の解決に時間が必要になるので、1週間前までにわからない部分はリストアップしておいていつでも聞けるタイミングで聞けるよう準備しておきましょう。
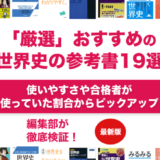 世界史のおすすめの参考書ランキング19選を東大生が徹底解説!【大学受験】
世界史のおすすめの参考書ランキング19選を東大生が徹底解説!【大学受験】 世界史の定期テストで高得点をとる勉強法

世界史の定期テストで高得点を取るには他の教科とは違った対策が必要です。ここでは絶対に世界史の定期テストで高得点が取れるような秘訣を紹介していきます!
世界史の定期テストには範囲チェックが欠かせない
まずは定期テストに出る範囲を確認しましょう!世界史は全ての範囲を勉強しようと思うと量が膨大で時間もかなりかかってしまいます。
しかし、世界史の定期試験は全ての時代・地域が範囲として出題されるわけではありません。
世界史の定期テストではむしろ中国史や西洋史など絞られた範囲の時代・地域の問題が出題されます。まずはテストの範囲の時代・地域を把握しないことには勉強の方向性を決めることができません。
そのためまず世界史の定期テストの範囲を学校の先生の情報やすでに決まっている範囲などから事細かに把握するようにしましょう。
世界史の用語の暗記は地道に行う!
世界史の定期テストの中でも特に期末テストの世界史の範囲はとてつもなく広いです。ですので定期テストの時だけ暗記したとしても9割を超える高得点は見込めないでしょう。
ただし、ただ勉強するのではなく効率的に勉強することができるなら、定期テストの時だけの勉強で十分に9割取れるでしょう。
世界史の用語を時代やイメージに関連付けて覚える
スタディチェーンが考えた世界史の勉強法の中に用語を印象付けるという方法があります。名前が長い人物だったな~、聞いたことある戦いだな~といった具合に頭の片隅に残るぐらいの記憶があれば定期テストの時に思い出しやすくなると思います。
そうすれば、世界史の覚える用語も減りより効率的な世界史の勉強につながると思います。
定期テストの世界史で9割取るにはノートを活用した勉強法が重要
世界史の覚えることがたくさんある分、勉強を進めていく中でこれもう覚えたという部分もたくさんあると思います。そこで、まだ覚えていない世界史の用語や事件と自分がなかなか覚えられない箇所に集中することもとても大切です。その世界史の定期テストの勉強において自分がやるべきことに集中でっきるようになるのが復習ノートです。
いつでも移動している時などに見れるようにして、いま自分が苦手、覚えられていない世界史の用語をそこにまとめるのは非常に効果的です。
世界史の定期テスト対策はどれだけイラストや流れの図が作れるかではなくノートにどれだけ今自分が覚えていない用語をまとめてそれを減らせるかという勉強法が大切です。
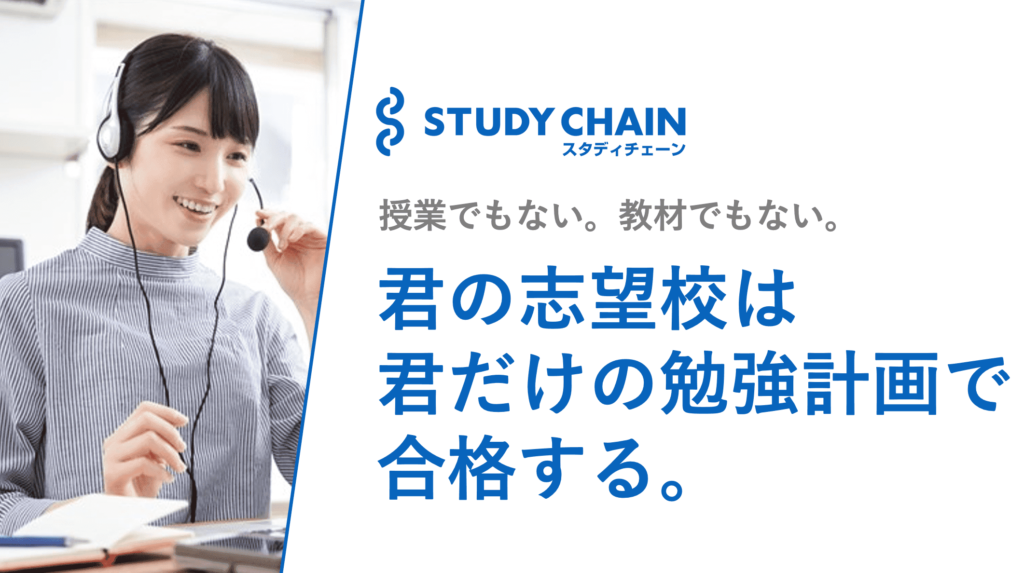
世界史の定期テストで高得点を取るための最初にやるべき勉強法
世界史の定期テストで高得点を取るために必要な勉強法について解説します。
学校の先生からの世界史の定期テストの情報を収集する
世界史の定期テストの範囲や出題の傾向に関する情報を学校の先生などから徹底的に集めましょう!世界史の定期テストについてなにも知らなければ、なにをどれくらい勉強すればいいか、どこが出題されるのかなど定期テストの具体的な部分がわかりませんよね。定期テストでは前日の一夜漬けや勉強法よりも授業でどこが出るか聞いておくことが大切です。
そこで世界史の定期テストに関する情報を集めると、まず自分が定期テストで決めた目標の点数に対してやるべきことが具体的になります。
「ここ定期テストで出すよ」と学校の先生が言っている場所があるならそこは絶対にやるべきですし、ここは出題しないと言っていたならそこまで重点的にやる必要はないでしょう。定期テストは受験勉強と異なる点は初めから出る点がある一定わかっているということです。
定期テストの世界史はやみくもに暗記よりも、大きな流れを確認しよう!
教科書も分厚く学ぶ内容がぎっしりの世界史。当然定期テストのテスト範囲も広くなり,世界史の年号や人名を片っ端から暗記していったのでは、さすがに辛いでしょう。
いきなり世界史の細かい知識を暗記するのではなく、定期テストの世界史の範囲を区切って、まずは“どんな原因で何が起きたか,その結果どうなったか”という定期テストの世界史の範囲の時代ごとや地域ごとにおける大きな流れをつかんでいきましょう。
それから世界史の教科書やノート、プリント、資料集などを活用して,細かい知識を身につけていきましょう。世界史の効率的な勉強法の鍵は一気に全部やるのではなく、3日単位などで今日は中国の殷から周までなど範囲を区切って勉強することが大切です。
定期テストの世界史で9割取れる勉強法<実践編>
定期テストの世界史の勉強法の流れを具体的に説明します。
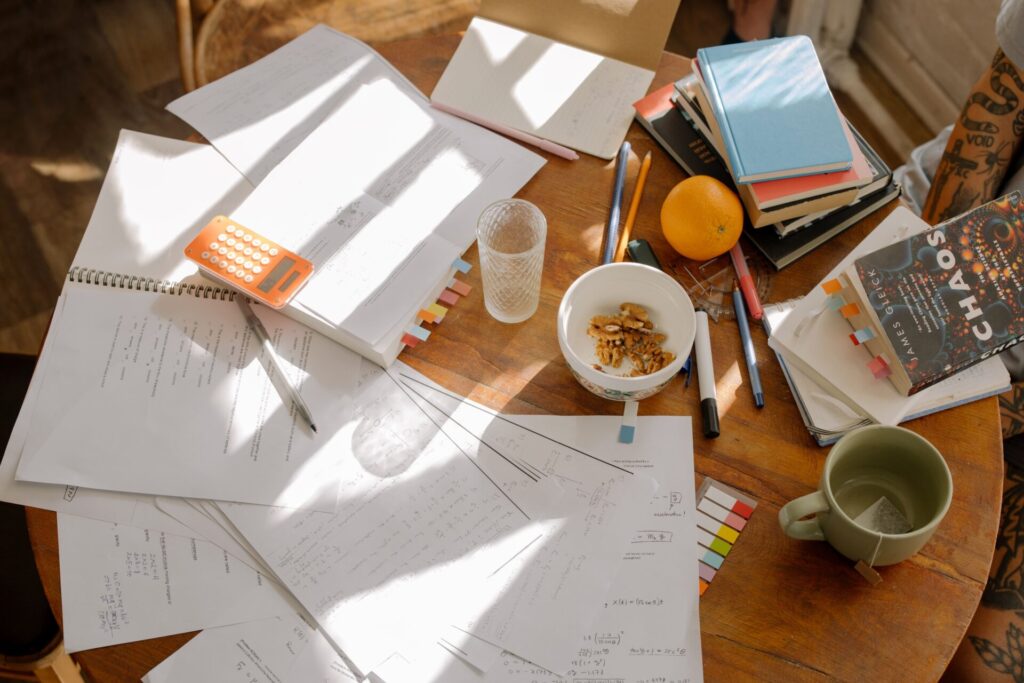
世界史の定期テストの範囲全体のタテとヨコの流れをインプットする
定期テストの世界史ではヨーロッパ,中国,西アジア,南アジア…など、中間や期末によって範囲はバラバラですが、1つ1つさまざまな特徴があります。
1回の定期テストの範囲でもたくさんの地域が登場します。そのため、まずは地域ごと,国家ごとの歴史の大きな流れを確認する勉強法が重要です。具体的な勉強法としては、世界史の定期テストの試験範囲を覚えていくのではなく、世界史の定期テスト勉強ではいつまでにどの範囲を覚えるのかを把握しておくことがとても重要です。
そして、初めに勉強した大きな流れに関連づける形で、試験範囲の中の必要な年代や人名や地名などを整理するようにしてください。世界史はそういった年代や人名などをまとめる定期テスト用のまとめノートを作る勉強法も非常に効果的です。
世界史の教科書の太字は定期テストに頻出
世界史の教科書で太字になっているところは,歴史の流れの中で重要な役割を持つ用語です。世界史における事件名や人名,地名など,定期テストでも問われやすい事項なので,確実に押さえておきましょう。
また定期テストの世界史では,都市名や国の領域など,地理的な位置を把握していることがとても重要なので,教科書に載っている地図にも要注意です!
世界史の用語を語呂合わせで覚える
定期テストの範囲の世界史の用語は覚えにくい上かなりの量があります。ですので、特に年号は語呂合わせを使って暗記することで暗記する量も減るし何より楽しく覚えることができます。
自分で世界史の語呂合わせをつくったり、友達と世界史の用語の語呂合わせを教えあったりすれば脳に記憶されやすく世界史の定期テスト中にも思い出すことができます。

世界史の定期テストの前日に一夜漬けで詰め込む勉強法
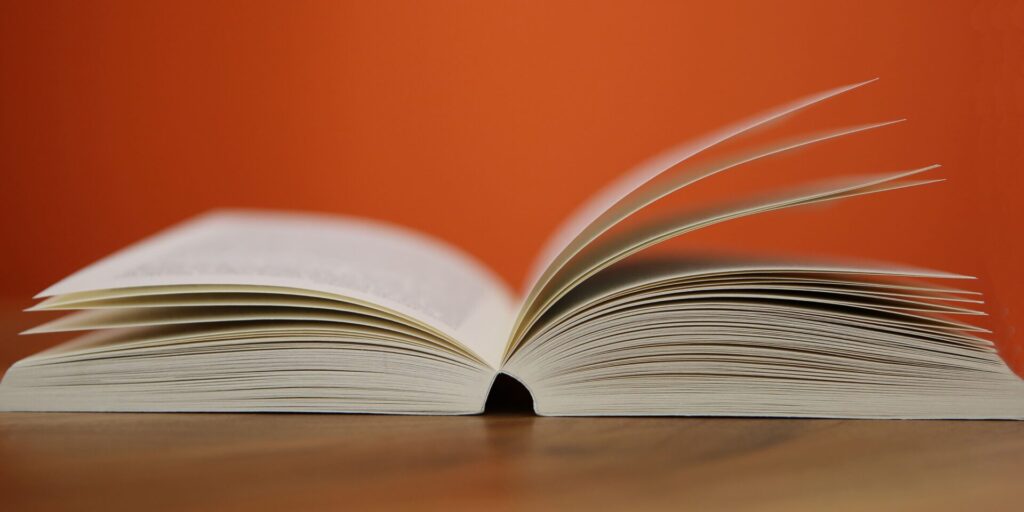
定期テストの全体の勉強計画を立てても、中々うまく遂行できなかったり、英語や数学などの重い科目に引っ張られ、暗記科目である世界史が後回しになって世界史の定期テストが明日なのに、全然終わってないといった経験のある人も多いのではないでしょうか?
そして、世界史の定期テストの当日の朝、徹底的に暗記・復習してください。他の計算が必要な数学などは定期テスト直前に復習したとしても、定期テストの点数UPに繋がるということはあまりありません。
しかし、世界史はやればやるほど点数が上がる科目です。直前までみていた世界史の教科書に載っていたことがテストに出るといったこともしばしばあります。
世界史の定期テスト対策の一夜漬けの勉強法のコツとしては、教科書の黒字部分をノートにまとめる。そして、一問一答形式で1つ1つ潰していくようなやり方をおすすめします。
やりがちな典型的なダメな定期テストの世界史の勉強法
やってはいけない世界史の定期テスト対策の勉強法を解説します。
世界史オタク君になるな
これは世界史に限らずの話ですが歴史を受験で勉強している中には「歴史オタク」と言われる人が多発します。歴史科目はやればやるほど点数にもすぐにつながり目に見えて勉強の効果も出ます。更に、国語や英語や数学と比べて頭を使わない科目ですので、勉強も疲れずに楽にできます。
それ故、多くの受験生は一番大切な英語をおろそかにし歴史の勉強ばかりしてしまいます。その歴史をやりたくなる感情を抑えて、先に述べたゴールを意識して世界史の勉強に取り組みましょう!
私も所謂世界史オタクだったため、やりたくなってしまう気持ちはわかりますが、志望校で花のキャンパスライフを送るためと割り切って頑張りましょう!
世界史用語集使い倒し勉強法
世界史用語集使い倒し勉強法は「世界史オタク君」の進化系です。用語集を初めから読んでいきマーカーを引いていくという勉強をし始める人が受験期後半になってくると出てきます。本当にそんな効率悪いやり方する奴いるのかよと思うかもしれませんが、結構な割合で本当に出てきます(笑)
この記事を読んでくれた人は受験期後半になって精神的に疲れても世界史用語集を一から読んでいくといった気の迷いは起こさないでください(笑)
塾講師目線の伸びなかった生徒に共通の世界史の勉強法
伸び悩んだ生徒で共通だったのが、自己満足の世界史の勉強法をしていたところです。学校で板書したノートをわざわざカラフルに地図も書いてまとめなおすといったようなただの作業に精一杯時間をかけて取り組んでいました。
世界史は単純暗記の苦行をするのではなく、流れを理解し楽しく効率的に暗記する方がよいと上で述べている以上矛盾になってはしまいますが、やはり世界史は暗記科目ですので「泥臭く」裏紙に書きまくるといったような勉強法も必要だということを忘れないでほしいです!
定期テストの世界史でよくある悩みへの知恵袋
ここでは世界史の定期テストの勉強法について受験生や高校生からよくいただく質問や悩みについての回答を知恵袋形式にてしていきたいと思います。
世界史は定期テストの勉強が受験勉強にもつながりますか?
世界史の定期テストの勉強についてですが、学校の定期テストの勉強で得た知識がそのまま受験勉強にもつながります。定期テストでは特にいつの時代に誰が何をしたかなどの用語は確実に忘れないようにしましょう。定期テストの本番で9割取れたなら7割程度は定期テストが終わった後も覚えているでしょう。それくらいで十分です。
定期テストの世界史がしんどい、苦手という人もここでがんばることで、定期テストの世界史でいい点数を取れるだけでなく、受験勉強でも優位に立てるという意識をもって取り組みましょう。
用語は覚えたけど、時代の流れが覚えられません。
世界史の定期テストの勉強では、特に用語の暗記を時代の流れに当てはめていきながら行うことがとても大切です。ただし、最初から時代の流れと同時に用語を習得する勉強ができるのは難しいです。
定期テストの勉強やっていく中でどうすれば世界史の中国史、西洋史など各分野それぞれに分けた時に最速でインプットできる方法を見つけていきましょう。まずは用語を習得して、次に年号をおおまかでも覚えてから、地域の流れや時代の流れを理解しようとすることが大切です。
定期テストの勉強法の一覧【世界史、日本史、地理】
定期テストでは社会2科目が同じ時期のテストであるということもよくあると思います。学校によって定期テストのシステムは大きく変わってくるとは思いますが、今回は世界史以外にも定期テストの勉強法を紹介します。
▼日本史の定期テストの勉強法はこちら
▼地理の定期テストの勉強法はこちら
まとめ
世界史の定期テストの勉強法について解説しましたが、これから世界史の定期テストの勉強をどうすればよいのか理解できたでしょうか?どうしても膨大な範囲に対して「もう無理だ」と感じている人もいたとはおもいますが、大切なのはいつまでに何を覚えるかのスケジューリング、計画とどう勉強と復習をするのかの勉強法です。
もし定期テストと同じように受験勉強においても勉強法や勉強計画について悩んでいるという方には東大志望なら東大生、早稲田志望なら早稲田生というように「志望校の先輩」が勉強法や勉強計画の指導をしてくれるスタディチェーンというオンラインの塾がおすすめです。