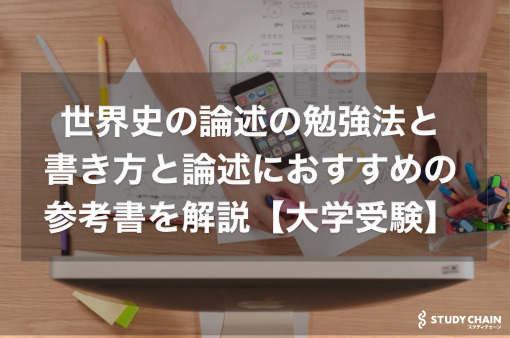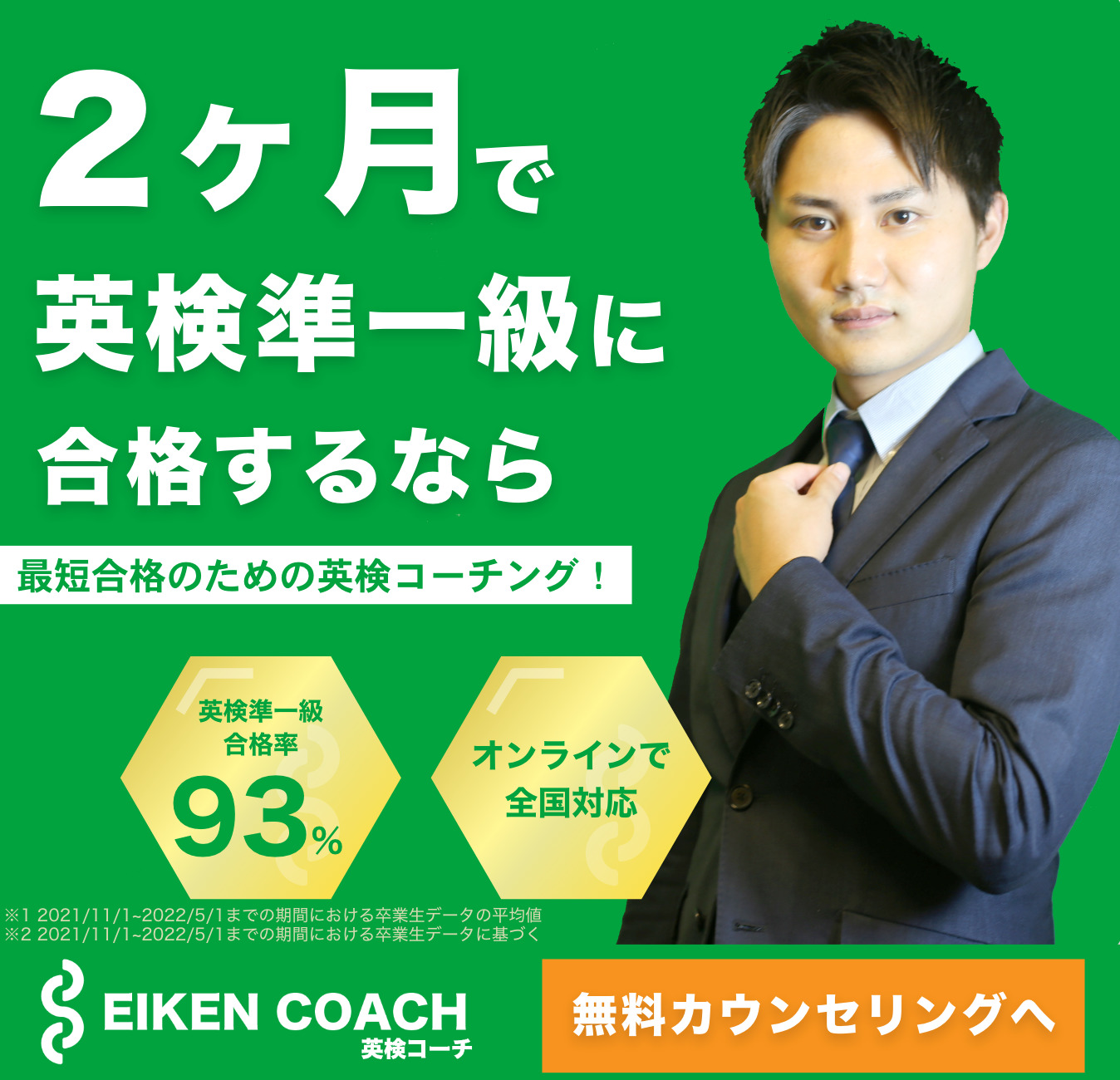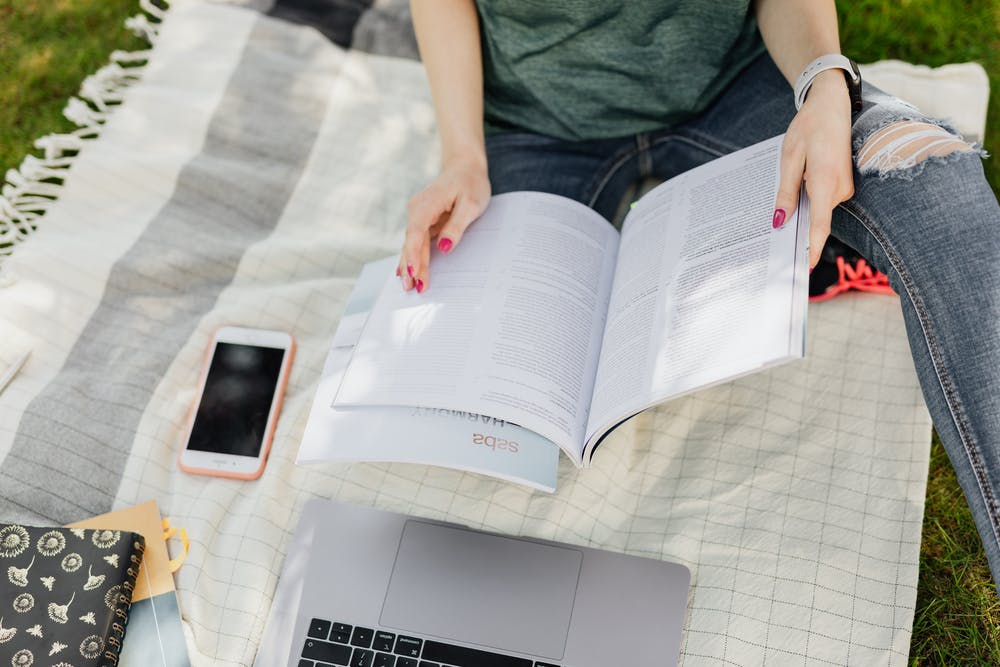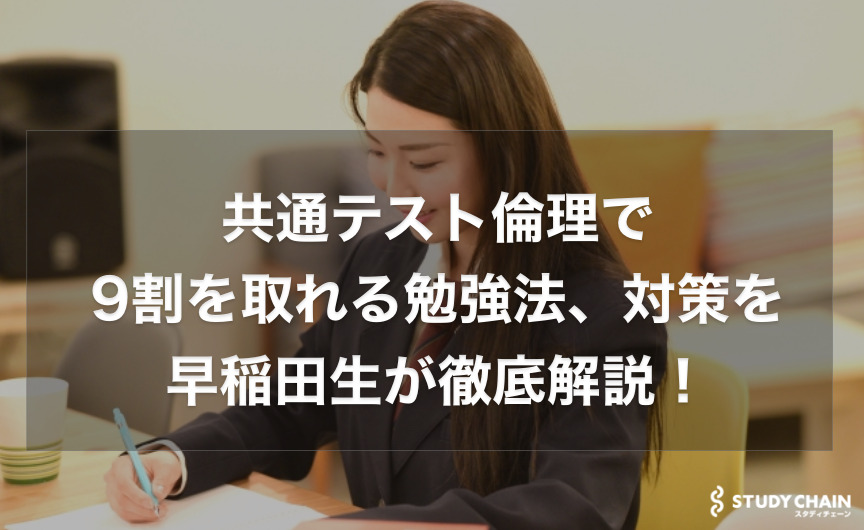大学受験の世界史の論述において大切な勉強法と書き方を徹底解説します。世界史の論述対策におすすめの参考書や難関大に合格する上で必要な世界史のインプットとアウトプットの方法を徹底解説します。難関大の二次試験もしくは本試験で世界史の論述が必要な方はその特徴や対策をぜひ参考にしてみてください。
[大学受験]世界史の論述の形式と特徴
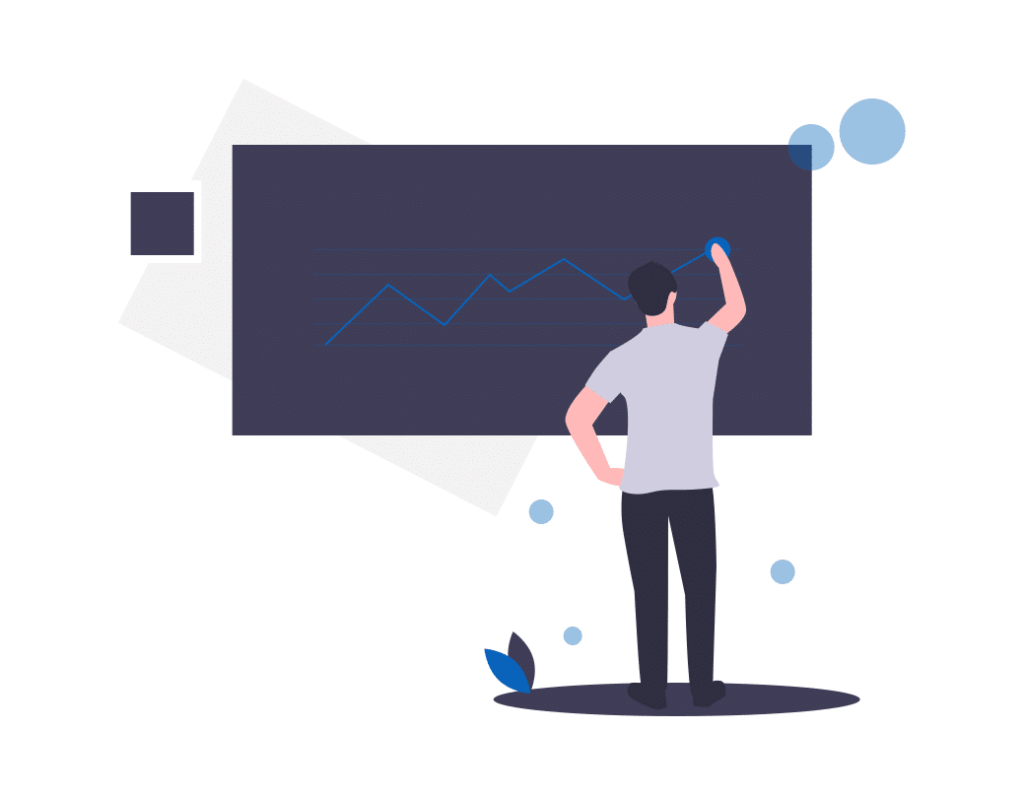
世界史の論述は志望大学によって特徴は大きく分かれます。そのため、論述の勉強法も志望校やあなたの使っている参考書などによっても大きく変わってくるため、ぜひ今回の世界史の論述の勉強法や書き方を参考にして高得点が取れる自分にあった勉強法を見つけてください。
世界史の論述問題は文字数別に分かれる
まず、世界史の論述問題の種類についてですが、20~100字程度で簡潔な文章のものが小論術と呼ばれ、150文字程度の論述が中論述と呼ばれます。そして、600字もの長い記述を求める大論述と呼ばれるものまであります。
- 「小論述」・・・100字に満たない短めの論述
- 「中論述」・・・150字程度の分量の論述
- 「大論述」・・・300字を超える特に分量の多い論述
大きく分けると世界史の論述というのは文字数別に3種類に分けることができます。
形式もさまざまで、指定語句が示されるものや、提示された史料や地図から読み取れることを参考に論述するよう求める問題もあります。
世界史の論述ができるようになるには4つの力が大切
世界史の論述で合格点を最速で取るために習得する必要があるのは「知識・過去問・記述力・読解力」の4つです。また、世界史の論述問題といってもさまざまです。
一問一答やナビゲーターを通して知識をインプットして、大学の過去問をみて志望校の傾向を知り、実際に世界史の論述の問題集を通して記述力を鍛えるのが大まかな勉強法です。
世界史の論述の重要ポイントとコツ
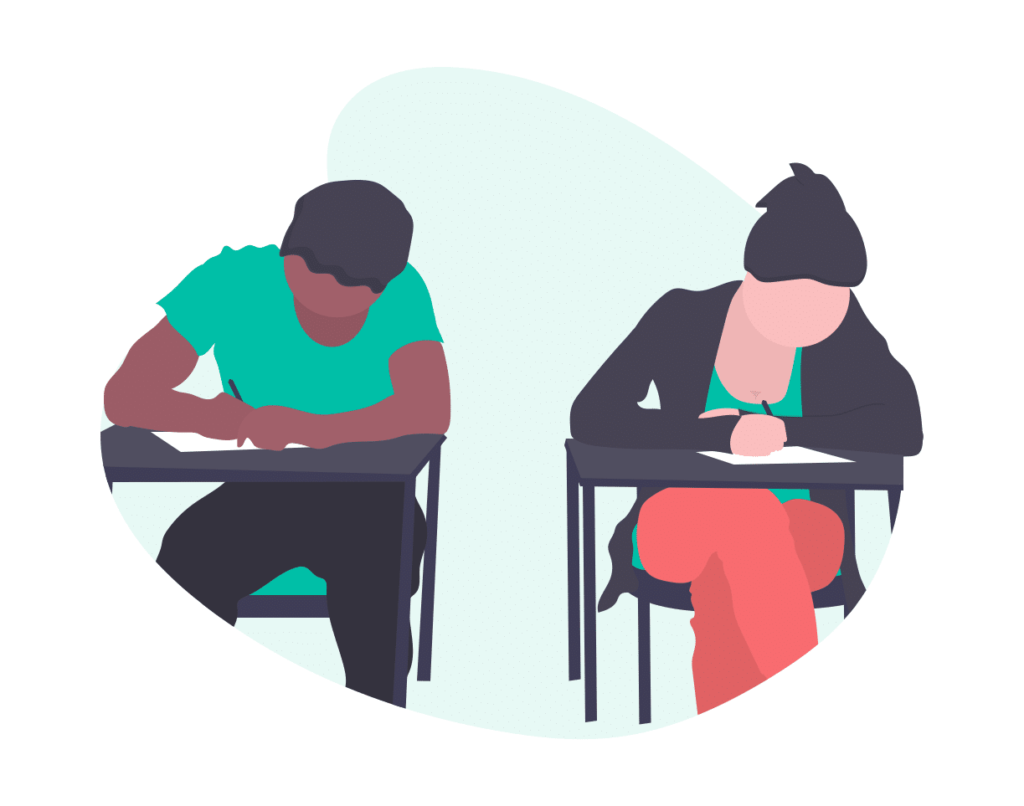
世界史論述が解けるようになるためには、まずは世界史の一問一答レベルの基礎知識の定着や、共通試験・私立大学入試レベルの問題を解くための学力養成が必要です。
理想的には、高2の秋ごろからインプットを始めておくべきでしょう。基本的には授業進度に合わせてインプットを進めていってよいですが、通っている高校の授業進度があまりに遅く、センター直前になってようやく通史が終わる、というような場合は自学で勉強を進めていきましょう。
世界史の論述で頻出の分野は近現代
そして、古代から現代までの全時代が論述の出題範囲となるものの、特に多く出題されるのは近現代をテーマとする問題です。近現代が世界史の論述では頻出ということからも、まだ通史の学習を終えていない段階で論述対策に力を注ぐことはあまり効果的ではないと言えるのです。
過去問対策は世界史の論述の合格レベルにいけるかの運命を分ける
世界史の論述対策をする上で先ほど言ったようにどの大学の過去問を解くかによって大きく変わるため、受験勉強のスケジュールを考える上で過去問にいつ入れるか?とどの志望校を目指すか?はとても大切です。もし東京大学や京都大学、一橋大学の世界史を選択する予定であれば9月ごろから過去問を使った学習をする必要があります。
過去問を通して頻出の分野と解答例を必ずチェックすること
ただ旧帝大以下の大学を志望している人はまずは基礎固めをナビゲーターなどでみっちりとした上で過去問をみてどの時代や地域が頻出なのかを確認したり実際の解答例を確認することがとても大切です。
論述は合っているかどうかも大切ですが、どうしても受験勉強をしていると論述は主観的に判断してしまうことが増えるため自分の志望校の世界史の解答例は必ずチェックしておきましょう。
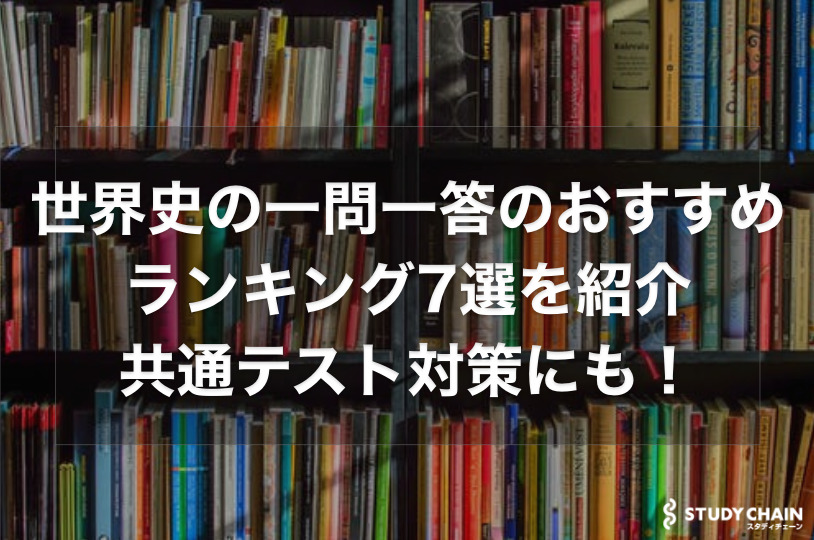 世界史の一問一答のおすすめランキング7選を東大生が解説!定期テスト対策にも!【大学受験】
世界史の一問一答のおすすめランキング7選を東大生が解説!定期テスト対策にも!【大学受験】

世界史の論述の頻出問題を確実に解けるようになる勉強法
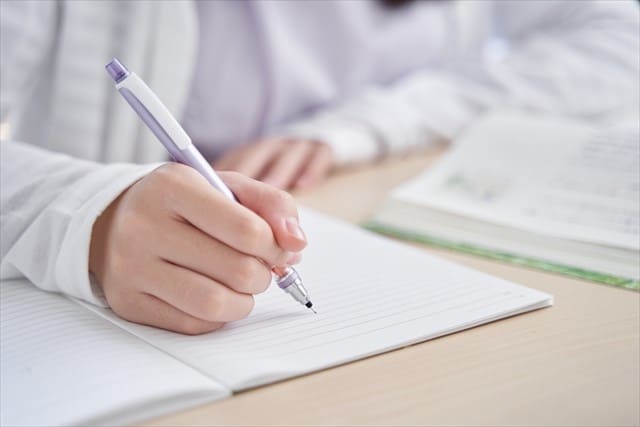
世界史のアウトプットの開始時期は、知識のインプットがどれだけ進んでいるかによって決まります。
一般的には、高校3年生の秋までに始めることを1つのタイムリミットとしましょう。高校3年生の夏までは基礎固めに専念するのがよいでしょう。
東京大学や一橋大学など、特にハイレベルな論述が出題される大学を受験する場合は、もっと早く、高校3年生の春には対策を始めて論述に慣れておくことをおすすめします。
ただし、国公立大学の受験生は共通試験対策に力を注ぐことが優先事項です。論述の対策ばかりで他の科目や世界史の基礎がおろそかになり、第二次試験に進むことができない(足切りされてします)のは本末転倒になってしまうので気をつけましょう。
論述で縦の流れは頻出なので必ず早めにやろう
「縦の流れ」とは、各国で起こった出来事を時系列で見る流れです。縦の流れは世界史を勉強する上で基礎となるため、横の流れを掴む前に勉強することをおすすめします。
縦の流れを追うことによって、1つの国の歴史や出来事を物語のように把握することが可能です。その国でどのようなことが起こったのかを掴む際に役に立つでしょう。
横の流れの論述は難易度が高いが勉強法次第
「横の流れ」とは、ある国である出来事が起こった際に、他の国ではどのようなことが起きているのかという流れです。世界史を勉強するにあたって、さまざまな国の時系列が混ざって混乱するという方は横の流れを理解できていない可能性があります。
縦の流れだけで世界史を覚えてしまうと、年代などがバラバラになってしまいます。 横の流れを把握するためには、ノートを1冊用意して自分で年表を作ることをおすすめします。
年代を書いた後、その時代に起きた出来事を記述しましょう。自分で年表を作ることによって、頭の中の知識が整理されます。
また、空いているスペースに地図を添えておくと、より理解を深めることが可能です。
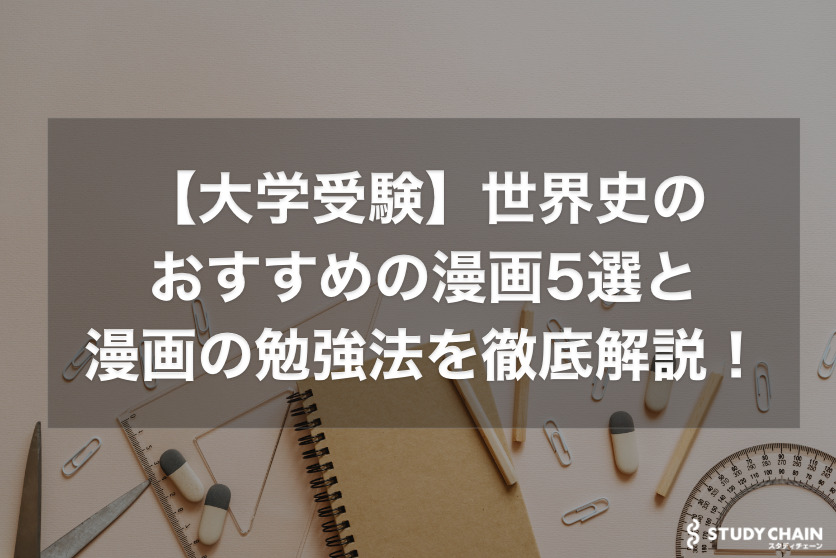 【大学受験】世界史のおすすめの漫画4選と漫画の勉強法を徹底解説!
【大学受験】世界史のおすすめの漫画4選と漫画の勉強法を徹底解説!
世界史の論述の勉強におすすめの参考書
世界史の論述対策におすすめの参考書を紹介します。
みるみる論述力がつく世界史

みるみる論述力がつく世界史は「基本編」「発展編」に分かれた構成です。まず「基本編」では「よくある解答」に対する採点結果とどこがだめだったのかを詳しく解説されています。そのため、具体的にどの部分を改善すべきかがわかるようになります。また、みるみる論述力がつくる世界史では合格答案に必要な知識について教科書の該当ページを利用した空欄補充が掲載されています。
そして「発展編」ではそれぞれ頻出の世界史の論述の問題をピックアップして応用レベルに対応するための論述力や論述の書き方が詳しく解説されています。

少しずつ論述を始めたい人におすすめは段階式 世界史論述のトレーニング

100字未満→100~180字論述→200~250字論述→300字以上の大論述とだんだん字数を増やしていくので、初心者でも無理なく取り組め、最終的には実戦的な論述力が身につけることができるオススメの一冊です。
また、採点ポイントが細かく記されているので自己採点もしやすい内容となっています!
世界史の論述をとにかくやり込みたい人におすすめは判る!解ける!書ける!世界史論述

判る!解ける!書ける!世界史論述は全部で4章構成になっています。
- 第1章「入門編」では、世界史の論述をするにあたっての基礎固めの内容になっています。
- 第2章の「通史研究編」では、全時代・全地域においてどういう書き方や流れを抑えれば論述ができるようになるかわかるようになります。
- 第3章「テーマ史研究編」では、世界史の中でも基礎レベルを超えた応用ができるようになります。
- 第4章「練習問題」では、難易度の高い世界史の論述の書き方が掲載されています。
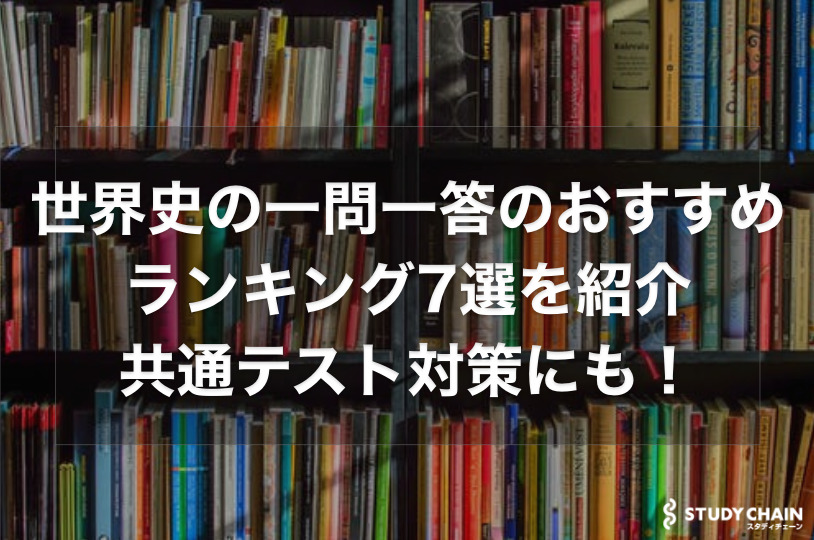 世界史の一問一答のおすすめランキング7選を東大生が解説!定期テスト対策にも!【大学受験】
世界史の一問一答のおすすめランキング7選を東大生が解説!定期テスト対策にも!【大学受験】
世界史の論述対策は志望校の研究が重要

世界史の論述を出題する大学の多くは、例年似たような形式・分量を踏襲する傾向にあり、字数や形式が大幅に変わることはめったにありません。
そのため、世界史の論述対策では過去問の分析が非常に大きな意味を持ちます。また、自分の志望校と同じような問題形式の大学の過去問に取り組むことも有効な勉強となるでしょう。
このように志望する大学によって世界史の論述においてどんな対策をすればいいか、どこを重点的に勉強すべきかが大きく変わってきます。そのため、世界史の論述を最短でできるようになるためにやるべきことは自分の苦手分野の把握だけでなく志望校の特徴や頻出分野の範囲を調べ、そこから重点的に勉強するようにしましょう。
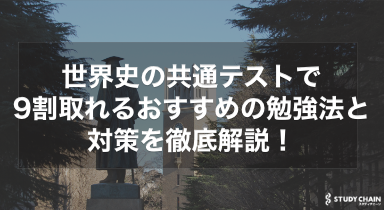 世界史の共通テストの勉強法を徹底解説!【大学受験】
世界史の共通テストの勉強法を徹底解説!【大学受験】
【大学受験】論述以外の世界史のおすすめ参考書

世界史の論述ができるようになるためには、ただ闇雲に年号や用語を暗記しても論述で点数が取れるようにはなりません。論述で高得点が取れるようになるために意識すべきことは、世界史全体の流れを掴むことです。
世界史の流れには、縦の流れと横の流れの2つの軸があります。そのため今回は流れをどうインプットしていけるかという点でおすすめの世界史の参考書を紹介します。
早慶レベルの論述をやりたい人におすすめタテから見る世界史

先ほど述べたように、世界史の勉強に大切なのは物事の流れを「タテの流れ」で見ることと「ヨコの流れ」で見ることの2点が重要となってきます。 この参考書では世界史の流れで大切なタテの流れを学べる参考書となっています。
「世界史の流れがなかなかつかめない…」という人へ。 世界史の教科書は古代~現代という時代の区切りで書かれているため、ローマの次はインド、その次は中国…とどんどん地域が飛んでいきます。そのため「通史の流れがイマイチつかめない」という悩みを抱えている人が非常に多いです。
この参考書では各国・地域ごとに通史を一気に整理して解説しているので、流れを簡単に理解することができます。 「ヨコ」を問う問題を解くためには、「タテ」の知識が不可欠です。
「ヨコのつながり」がわからない、という人は「タテの流れ」を理解できていないということが多いです!
MARCH以下を志望していて世界史の論述のためにサクッと要点を抑えたい人におすすめ時代と流れで覚える! 世界史

時代と流れで覚える世界史の中には頻出の分野をわかりやすく綺麗にまとめてくれています。
世界史の全体においてほとんどまとめられています。 特に左側のページは資料集のように世界史上の図や写真で説明されており、右ページに問題がある見開きの構成になっています。難関私大で出題されるようなあまり出てこないが勉強しておかないといけない単語などものっています。
世界史の基礎固めが終わった人におすすめヨコから見る世界史

先ほど述べたように、世界史の勉強に大切なのは物事の流れを「タテの流れ」で見ることと「ヨコの流れ」で見ることの2点が重要となってきます。ヨコから見る世界史では世界史の流れで大切なヨコの流れを学べる参考書となっています。世界史全体を時代ごとにヨコ割りにして整理し、同じ時代に他地域で起こった別々の出来事の因果関係を読み解いていきます。
特に上位校の入試問題では、世界史全体をヨコの流れを中心として構成された問題が主流となっています。また、世界史の知識量が重要と思われがちな正誤問題の対策も、世界史上の事件などのの横の流れを意識して学ぶことがカギとなります。
また、論述問題でも「ヨコ」の流れが多く問われるので、論述でなかなか点が取れないという人にもおすすめの参考書です。
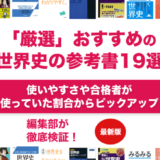 世界史のおすすめの参考書ランキング19選を東大生が徹底解説!【大学受験】
世界史のおすすめの参考書ランキング19選を東大生が徹底解説!【大学受験】