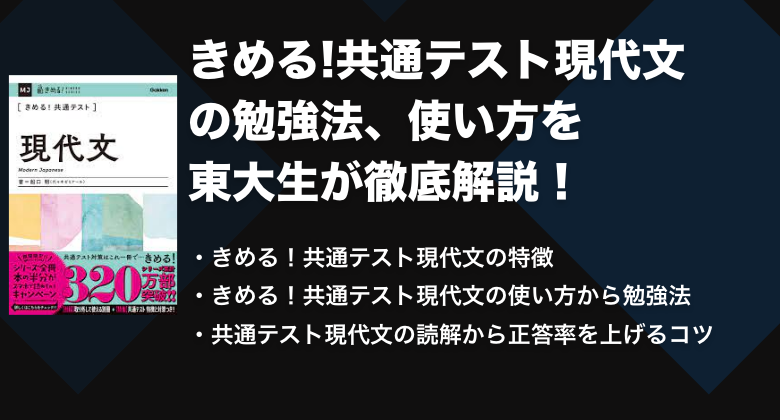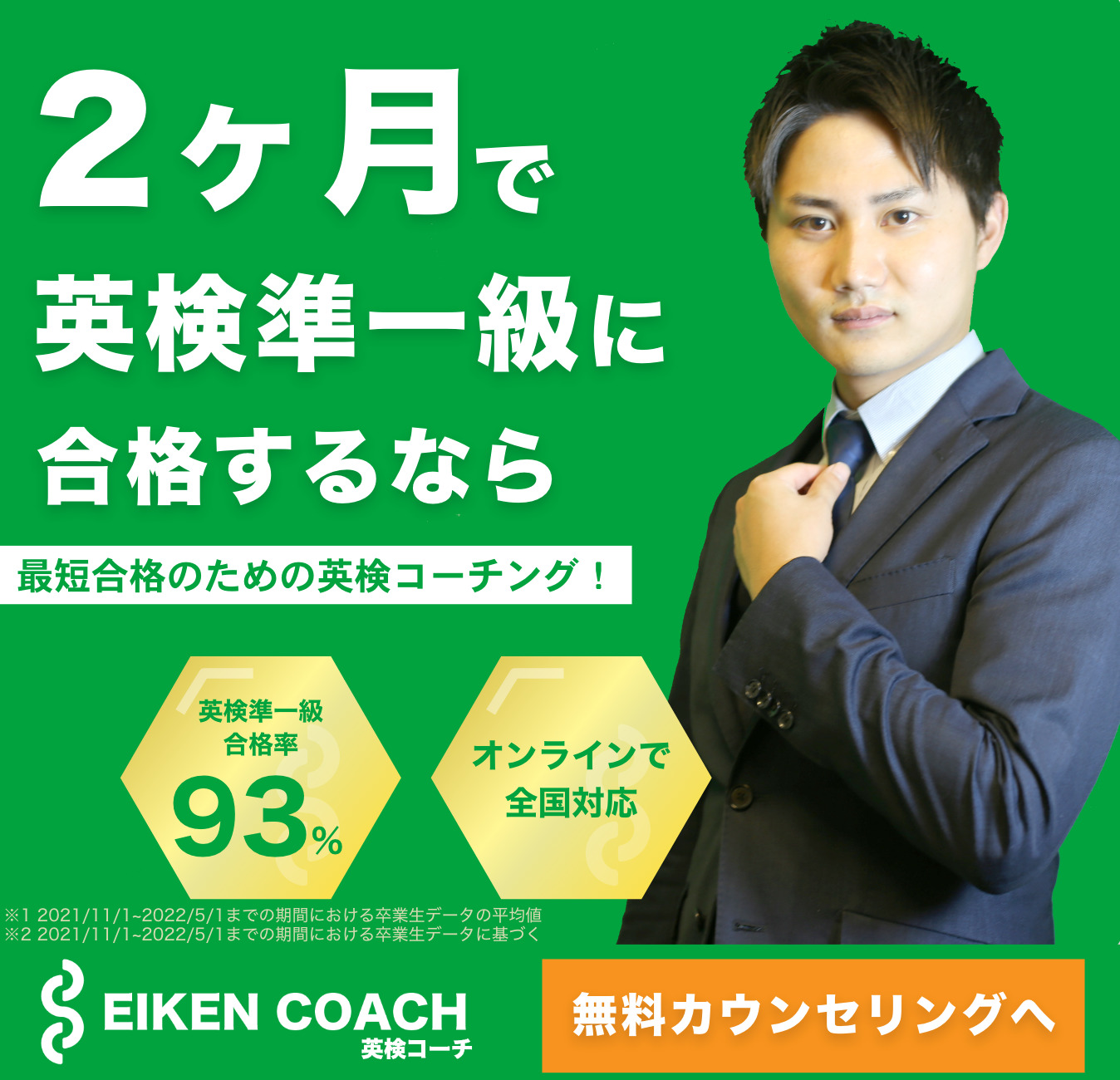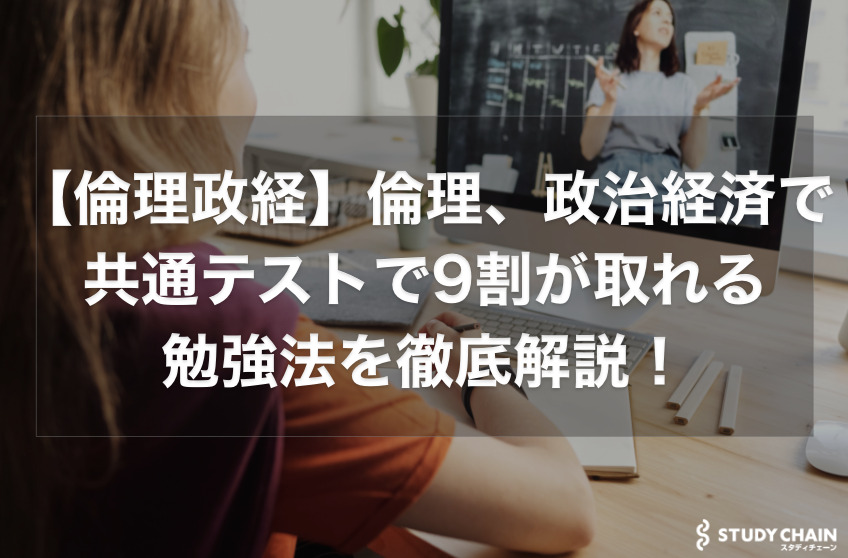決める!共通テスト現代文は共通テストで高得点を取るためにおすすめの参考書です。共通テスト現代文において重要な参考書選びの中でもしっかりと高得点をとって共通テスト利用や難関大合格につなげたいという方へ決める!共通テスト現代文の使い方や勉強法を徹底解説します。
きめる!共通テスト現代文の特徴
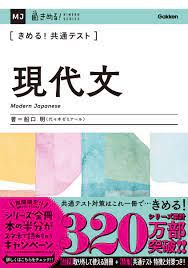
きめる!共通テスト現代文のおすすめの理由を説明する前にまずはきめる!共通テスト現代文はどういう参考書なのか?どういう受験生におすすめの現代文の参考書なのか特徴とポイントを一緒に把握していきましょう。
きめる!共通テスト 現代文の内容
第1部と第2部に分かれていて、第1部が評論、第2部が小説となっています。
- ①共通テスト現代文ってこんなもの
- ②第1部評論分析編
- ③第2部小説分析編
大雑把に分けるとこうなります。
共通テストの現代文がなかなか解けない、点が取れずに苦手意識があるという人も、この1冊で解き方を習得すればあらゆる共通テスト現代文の問題に対応できるようになります。
- きめる!共通テスト 現代文には共通テストの過去問題が評論・小説ともに収録されています。
- クセの強くない出題ばかりを厳選して収録しているので、共通テストの現代文の読解に必要な応用力が確実に身につきます。
- 赤本などの共通テストの過去問集よりも解説もずっと丁寧ですので、より多くの知識を身につけることができます。
きめる!共通テスト 現代文では、問題を解き終えたら解説を参考にしながらノウハウを取り入れることを意識の中心におき、自身の解答を見つめ直しましょう。また、決める!共通テスト現代文の習熟期間、つまり勉強期間は6~8週間と設定します。間違ったところの復習と苦手なテーマの特定もしっかり行いましょう。
きめる!共通テスト現代文の「第1部 評論」の特徴
- 第1部 第1章 「時短の技巧」
文字通り、時間短縮のための勉強法術です。
- 第1部 第2章 「解」の技巧
共通テスト現代文の答えを導き出すやり方を学びます。
- 第1部 第3章 評論攻略の全体イメージ
「読む」と「解く」の両方のアプローチを共通テスト現代文で最も大切な「設問を解くタイミング」を学んでいきます。
◆決める!共通テスト現代文以外にもおすすめの現代文の参考書が知りたい!という方はぜひ以下の記事をご覧ください。
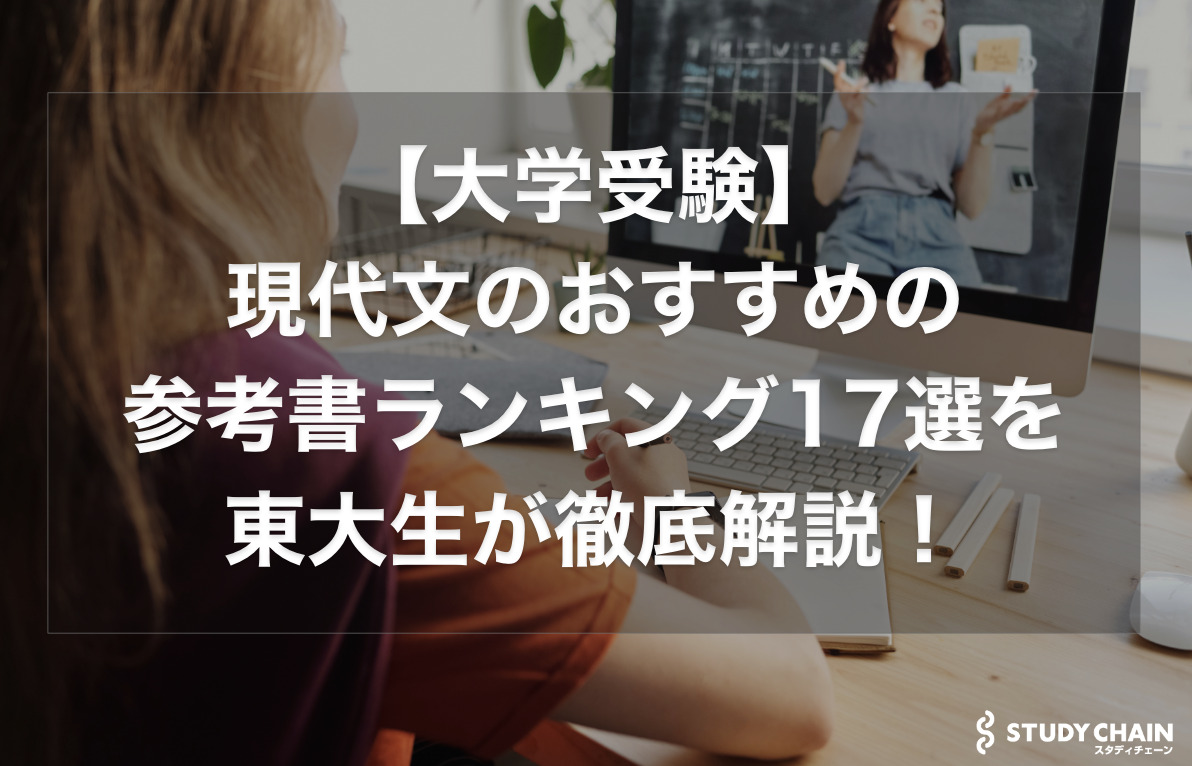 現代文のおすすめの参考書ランキング17選を東大生が徹底解説!【大学受験】
現代文のおすすめの参考書ランキング17選を東大生が徹底解説!【大学受験】 きめる!共通テスト現代文の「第2部 小説」
- 第2部 第1章「心情把握問題」の攻略
共通テスト現代文の小説において頻出である「心情把握問題」について学んでいきます。
- 第2部 第2章 小説問題攻略の全体的イメージ
評論と同じように「読む」と「解く」の両方のアプローチを共通テスト現代文で最も大切な「設問を解くタイミング」を学んでいきます。
- 第2部 第3章「解」の技巧きめる!共通テスト 現代文のポイント
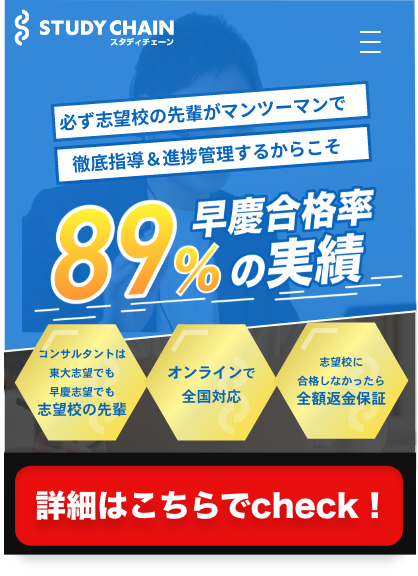
きめる!共通テスト 現代文はこんな人におすすめの参考書

そのため、共通テストが今、50~70点しか取れずに悩んでいる受験生におすすめの共通テスト対策の現代文の参考書です。自分の苦手な文章を中心に演習→理解→苦手の発見→克服を大切にしていきましょう。
『きめる!共通テスト現代文』はその名前の通り共通テストの現代文に特化した参考書です。
きめる!共通テスト現代文は、共通テストの現代文の秘訣→例題という構成になっており、インプットした読解法をその場で試すことができます。
きめる!共通テスト現代文は共通テスト現代文の考え方をマスターできる
そんな現代文の問題で 正解を導き出すまでの考え方がかなり詳しく解説されているので、現代文が苦手な人でも取り組みやすい問題集です。また、共通テスト対策は過去問題(黒本や赤本)よりもこちらを先に取り組んでもらいたいと思います。
共通テストの過去問よりも先にきめる!共通テスト現代文をやると効果倍増
「きめる!共通テスト国語 現代文」は共通テスト試験を受験するすべての受験生に取りくんで欲しい問題集です。
近年は入試方式が多様化しているため、私大に目標を絞った受験生にとっても、共通テスト現代文は重要なものになっています。共通テストの現代文の対策として多くの受験生が思い浮かべるのは、過去問題の演習だと思いますが、過去問題集に挑戦する前に、きめる!共通テスト国語 現代文に挑んでいただきたいのです。
赤本などの共通テストの過去問題集には、なぜその設問の答えが導き出せたのかといった解説は収録されているのですが、共通テストの問題をどうやって読み解けばよいかというそもそものノウハウについては掲載されていません。
このノウハウをきめる!共通テスト国語 現代文で身につけてから過去問題の演習に進むことで、より早く共通テストの形式に慣れることができます。
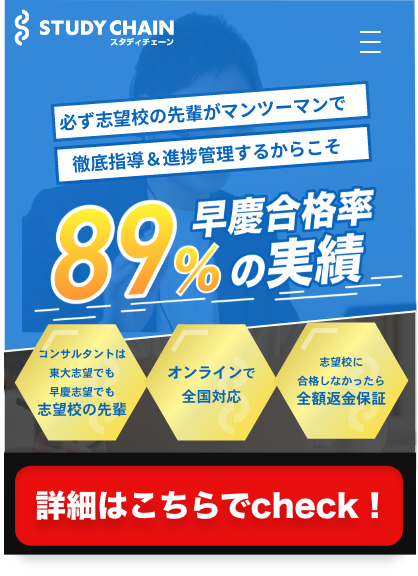
きめる!共通テスト 現代文のメリット
きめる!共通テスト国語 現代文は実際の試験に近い問題が多数収録されているため、受験生は自分の実力を正確に把握できます。また、きめる!共通テスト国語 現代文の解答解説によって、自分の弱点や改善点が明確になるため、効率的な対策が可能になります。
また、きめる!共通テスト国語 現代文は問題の難易度が幅広く、基礎から応用まで幅広いレベルをカバーしているため、初心者から上級者まで、幅広い受験生に対応できます。また、きめる!共通テスト国語 現代文ではテーマごとに分類されているため、自分の苦手なテーマにフォーカスすることができます。
きめる!共通テスト現代文の口コミ
共通テスト現代文を研究し続ける著者がその「本質」と、高得点獲得のための戦略を明らかにします。過去問11題を解きながら、「評論」と「小説」のそれぞれの読み方と解き方を身につけていきます。過去の共通テスト試験の漢字・語句問題をまとめた別冊つきです。
引用:決める!共通テスト現代文
ちょっと前の共通テストなら、「小説が得意だから速く解く」とか「漢文を15分以内で終わらせる」とか、そういうことができた。だから「その分を、評論を解く時間に回そう」とかいう工夫ができたんですね。でも今は、事実上それは厳しい。先にも言ったように、小説も長文化している、古文や漢文だって難しいことが多い。その上、評論も受験生にとってはなかなかの難問です。
引用:決める!共通テスト現代文
きめる!共通テスト現代文の具体的な使い方・勉強法
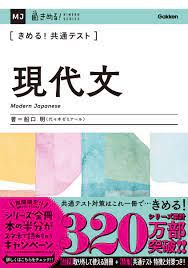
きめる!共通テスト現代文の解説と自分の解答・マークを見比べながら、相違点を洗いだす
現代文で大事なのは、単に答えが合っているか間違っているか(◯か×か)ではなく、答えの導き方が合っているかどうかです。
正解しても不正解だったとしても、必ず「なぜそれが正解になるのか?」の根拠をきめる!共通テスト現代文の解説を参考にしながら考えるようにしてください。最初のうちはきめる!共通テスト現代文の解説に書かれている解き方のポイントを真似する形で大丈夫です。
何で合ってたか、なんで間違ってたかまでを自分の言葉で説明できるようになれば完璧です。
本文の解説を読み、自分の本分の読み方とのズレを確認する
きめる!共通テスト現代文を解いてから答えの確認も大事ですが、「自分がどう本文を読んでいったのか?」も同じように解説を見ながら確認しましょう。
共通テストの現代文の問題を解くのにあたってもう一つ大事なのは、「適切に文章を読解できているかどうか」です。
ですから、きめる!共通テスト現代文の解説を読んで「自分は正しく文章を読めているかどうか?」というのを確認しましょう。これを一つ一つ丁寧に行うことで、確実に実力が伸びていきます。
必ず「なぜそれが正解になるのか?」の根拠を考えるようにしてください。それから徐々に、正解を導き出すプロセスや解答の根拠を自分の言葉で説明できるようにしていきましょう。
時間を計測して問題に取りかかる
その際、自分が解答の根拠に選んだ箇所や選択肢の判断基準を明確にしておくため、必ずマークを残しながら読み進める。
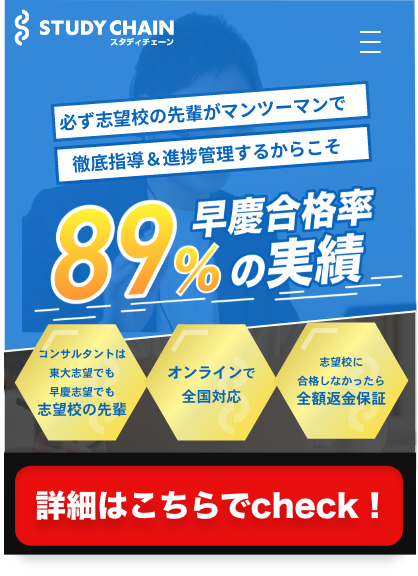
共通テスト現代文の読解のコツ
共通テストの現代文を読解するためには、
- 共通テストの評論文に頻出の難しいキーワードの暗記
- 共通テストの現代文の評論文、小説文の文章の読み方の習得
- 共通テストの現代文の問題の解き方や答えのカギの探し方、見つけ方の習得
まずは共通テストの評論文を解けるようになるよう現代文のキーワードのインプットにおすすめの現代文キーワード読解の使い方やキーワードの覚え方を以下で紹介しているのでぜひ参考にしてみてください。
 現代文の語彙の勉強法とおすすめキーワード参考書を紹介!
現代文の語彙の勉強法とおすすめキーワード参考書を紹介! まとめ
共通テスト現代文は感覚やセンスで解くような科目では決してないからこそ、先ほど説明した3つの力を習得できるようにしていきましょう。今回紹介したきめる!共通テスト現代文でも習得することは可能ですが、以下の現代文の勉強法もぜひ参考にしてみてください。
今回の記事だけでは、大学受験の勉強方法が具体的によく分からない!どんなペースで勉強したらよいのかよく分からない!という方には是非逆転合格専門塾の無料受験相談にて分からない勉強法や勉強計画についてなんでも相談してみることをおすすめします。

大学受験におけるライバルと差をつけて最短で合格レベルまで達するための勉強法と勉強計画に関する情報発信をしている。