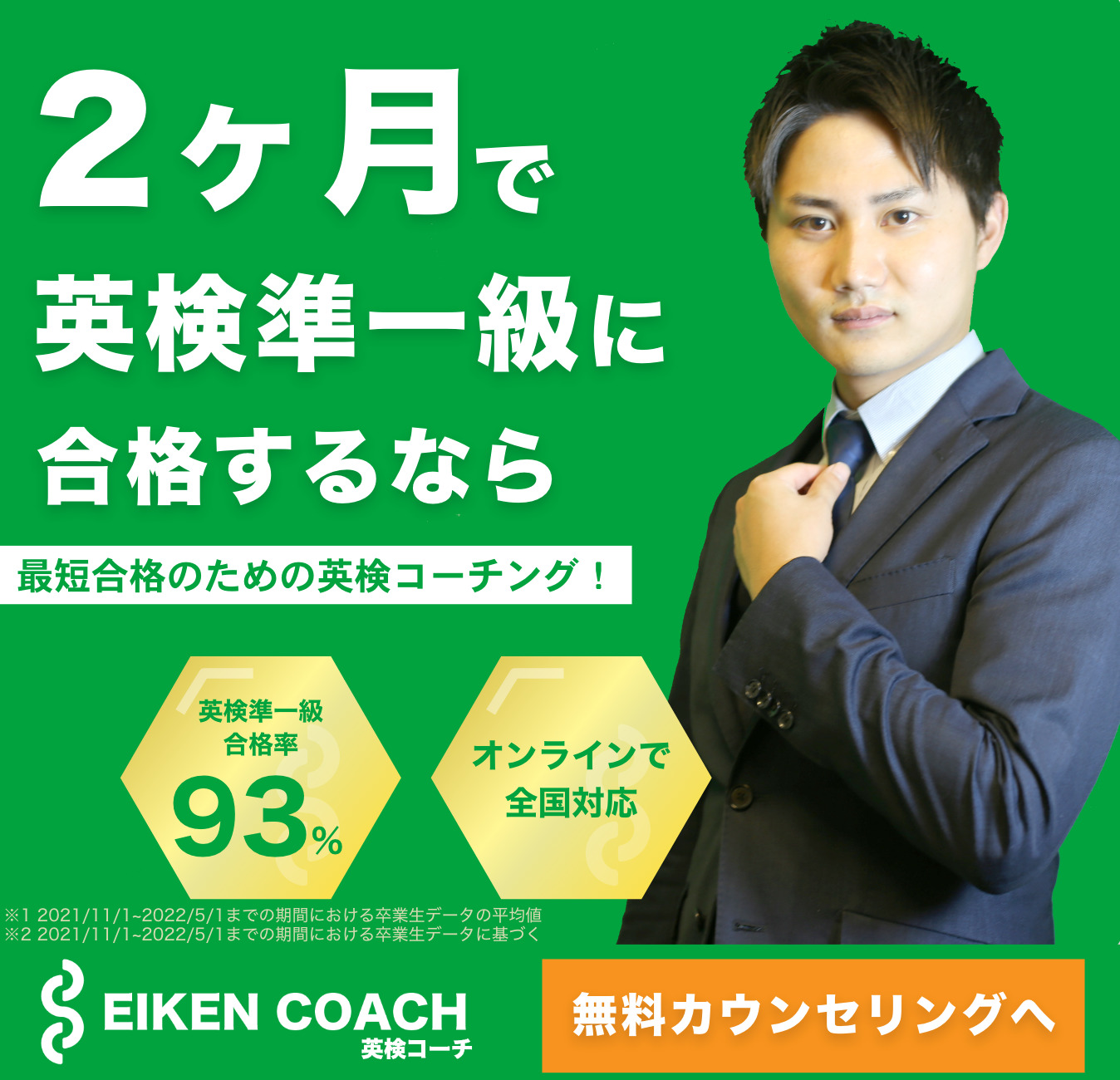受験生が迷う志望校の決め方を現役早稲田生が徹底解説。受験勉強を考える上でも将来を考える上でも志望校は本当に行きたいところを早めに見つけておくことが大切です。今回は、効率的に受験勉強を進めるための志望校の決め方を紹介します。
大学受験の勉強の前に志望校は?

みなさんは行きたい志望校をどうやって決めますか?
大学自体の分け方は主に2つあり、国公立大学と私立大学に分けられます。日本の大学は主に国立大学、私立大学、公立大学、短期大学に分かれています。
そして、国立大学と公立大学との差はあまりありません。そのため国公立大学とも呼ばれることも多いです。
その中でも、高校生の進学志望先として多い大学が国公立大学と私立大学になります。
現役大学生の方々が高校生だった頃、国公立大学と私立大学どちらを志望していたのでしょう?
現役大学生のみなさんに、国公立大学、私立大学どちらを志望していたか、とアンケートを行いました。まずは、アンケート結果をご覧ください。
【調査結果】「高校生のころ、国公立大学と私立大学どちらを志望していましたか」
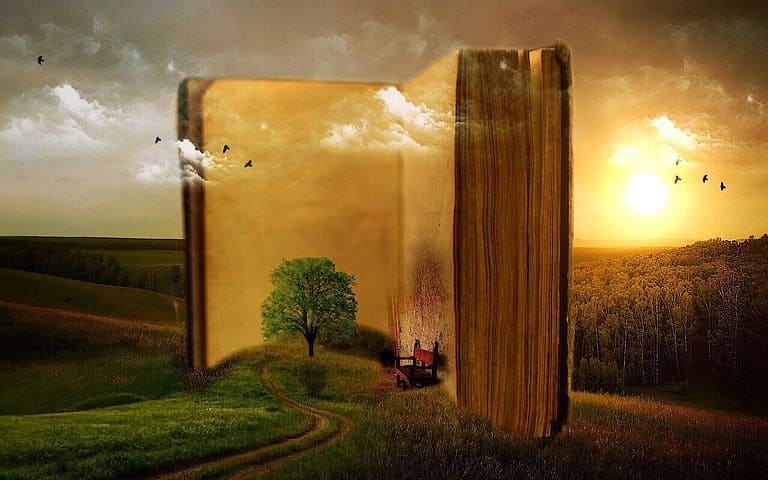
現役大学生を対象に「国公立大学、私立大学どちらを志望していましたか?」とアンケートを実施したところ以下のような結果となりました。
50%:私立
50%:国公立
志望校の大学の決め方
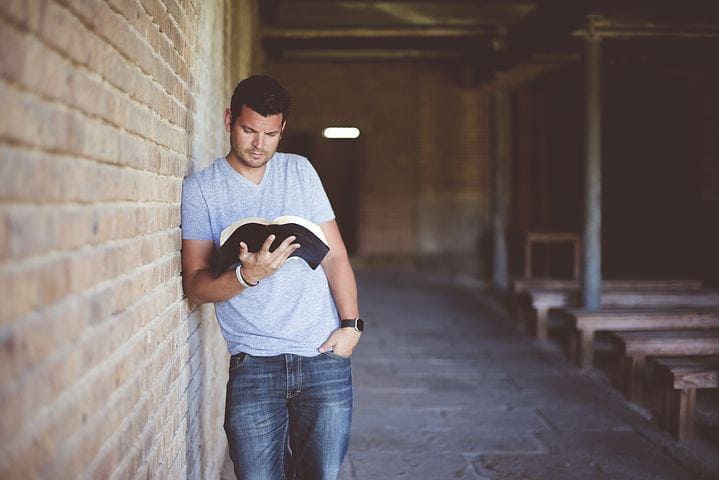
卒業後に進みたい分野が決まっているなら、それに関連する学部に必ず入ることをおすすめします。
大学受験における志望校は言わば「ゴール地点」、どの山に登るのかが決まればその山を登るのに必要な道具、知識、必要な能力などが明確になりトレーニングもしやすくなります。
やるべきことが明確になると自然とやる気が湧いてきてやる気になります。
志望校がどこなのかによって、東大なのか早稲田なのかによって対策(勉強の内容そのもの)が変わってくるので当然、大学受験に対する勉強計画も変わってきます。
志望校を選ぶ基準となるのは、
- ①国公立大学か私立大学か
- ②文系か理系か
- ③大学名よりも興味のある学部・学科を優先する
- ④大学の雰囲気・伝統・イメージ
の4つです。
現在、日本には大学が764大学もあり学部・学科にわけると2,307学部5,146学科にも上ります。
ひとりひとりにとって必ず学びたいものがどこかの大学には必ずあると思います
そして大学選択の際は、

志望校の決め方は学科→学部→大学の順番
受験生たちの中には、進路を決める際に学部(専攻分野)よりも大学名を重視する方々が一定数存在します。
つまり、興味のある研究分野よりも「大学のネームバリュー」を求める方々ですね。
どの大学も、学部によって偏差値や入試レベルにギャップがあります。
そこで、たとえ自分がまったく興味がない学部であったとしても、「とにかく有名大学の比較的偏差値が低い学部に入ろうとする」身の丈に合わないプライドを持った方々が出てきます。
ですが、大学のネームバリューばかりを追いかけ、学部学科選びを意識しなかった学生は必ず痛い目をみます。
興味の無い分野の学部に行ってしまうと、授業に行くモチベーションが本当になくなってしまうのです。
世の中には、沢山の大学があります。自分のやりたいこと、学びたい分野で大学を探していくと自分の行きたい大学が絶対に見つかるはずです。
日本の大学は主に国立大学、私立大学、公立大学、短期大学に分かれています。
志望校は受験勉強を始めるときに決める

志望校は大学受験に向けた勉強を始めるときに、一度決めておくと良いです。志望校を決めると「ゴール」が決まることになります。つまり「志望校に合格するための学力を身に着けるため」に、勉強をすれば良いのです。
志望校を決めずに目の前の勉強をしていても、学力を上げることはできます。ただ、より効率良く勉強を進めるためには、先に決めた志望校の入試に向けて学ぶほうが無駄がないのです。
「志望校を決められない」「志望校を決めるのは面倒」と思うことがあるかもしれません。ただ、それは単純に「志望校の決め方」を知らないだけの可能性があります。下で紹介するポイントを確認して大学の情報を見ると、興味をもてる大学が見つかるはずです。
まずは第1~3志望の志望校を決める
志望校を決めるときには、まずは第1~3志望まで決めると良いです。大学の情報を見ていると、どの大学が1番良いか決められなくなることがあります。この場合には最もレベル(偏差値)が高い大学を第1志望にすると良いです。その学力を身に着けることができれば、ほかの大学の入試にも対応しやすくなるためです。
また、興味のある大学が3つ見つからなくても、第1志望に近いレベルの大学を差し当たって2つ選んでおきましょう。「万が一第1志望の大学に対応できる学力を身に着けることができなくても、ほかにも良い大学はある」と考えられるようになると、受験勉強をするときに心の余裕が出てきます。「すべり止めの大学がある」と思えると、受験のプレッシャーを軽くすることができるのです。
途中で志望校を変更しても問題ない
志望校は途中で変更しても問題ありません。高校には高2や高3の時点で志望校を伝えることになるかもしれません。しかし最終的には、自分で受験する大学を決めることになります。
最終的に大学入試を受ける申込みをするのは、「高3の1月下旬から」です。それまでは志望校を変更することができるため、勉強をする中で、あらためて志望校について考えるのも良いです。
勉強をしていると、「思ったより成績の伸びが良い」という場合があります。このときには第1志望の大学を変更して、「興味はあるけれど今までの学力では目指せなかった」という大学も視野に入れると良いです。
ただ、志望校のレベルを下げるのは、あまりおすすめしません。途中で「自分には難しい」と考えて志望校のレベルを下げてしまうと、モチベーションが下がったり、難易度を下げた大学に学力を届かせることも難しくなってしまったりします。
志望校のレベルを上げたり、候補の数を増やすのは良いですが、レベルを下げるのは入試を申し込む1月直前にしましょう。現役生は高3の冬から急激に成績が伸びるため、最後まで諦めないことが大切です。
ちなみに「どうしても志望校を決められない」という場合は、まずは勉強量が多い「英語」と「数学」の勉強から始めて、これと合わせて志望校についても考えていきましょう。当面は自分の学力で目指せるレベルの大学を志望校に決めておき、あとから変更すると良いでしょう。できれば高3の夏休みまでには、志望校を決めるほうが良いです。
志望校を決める上で私立大学の特徴
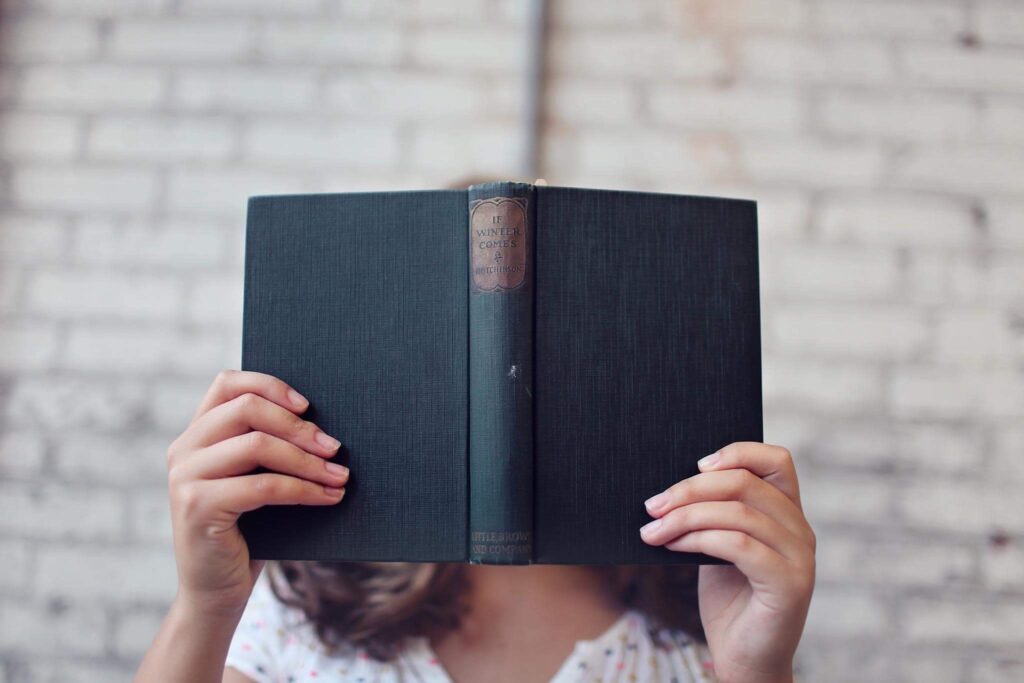
「私立」「私大」と言われます。六大学として名高い「早稲田大学」「慶応義塾大学」がこの「私立」にあたります。
文字通り、私人が運営している大学であり、国などはその運営には当たりません。
私立の場合、国公立に比べて校舎や設備、校風の自由度が高いという特徴があります。
キャンパスも美しく、通いやすいところにある傾向があるため、快適で活発な学校生活を楽しむことができます。
サークルが多く、充実しているのも特徴の一つです。
私立の場合、「どこにお金をかけるか」を自由に選ぶことができます。
そのため、「自分の目指す学部」が、「お金を掛けてもらっている学部」であったのなら、より充実した研究ができることでしょう。
また、私立大学の方がサポート体制が充実している可能性が高いとも言われています。
国公立に比べて就職の斡旋が多くあり、「社会人」としての活躍を見越して私立を志願する人もいます。
加えて、私立は国公立に比べて選択肢が豊富であるため、より自分の好み・進みたい方向に合った大学を探しやすいという特徴があります。
ただし、私立の場合は学費が高くなる傾向にあるので注意が必要です。
志望校選択の参考に国公立大学の特徴
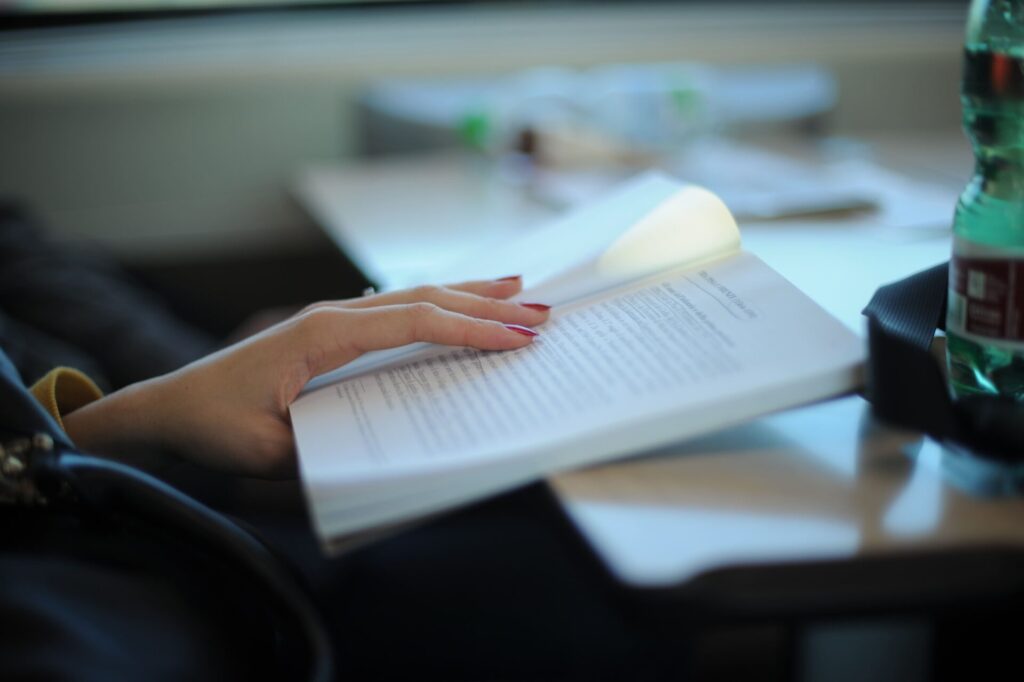
名実ともに日本のトップ大学である「東京大学」、関西の雄である「京都大学」などは、国公立大学(以下「国公立」)に分類されています。
運営団体が国や地方自治体になるため、学費が安いというメリットがあります。
この「学費が安い」というメリットは、特に「医学部」を志望するときに顕著になります。
医学部は非常にお金がかかる学部なのですが、国公立の場合は、ほかの学部とほぼ学費がかわりません。
そのため、経済的に余裕のない家庭であっても通うことができるというメリットがあります。
医学部の学費については、国公立と私立大学(以下「私立」)では10倍ほども変わるとされています。
また、国公立は大学内の設備が充実している傾向にあります。
もう少し正確に言うのであれば運営が国や地方自治体であるため、予算配分も決まっており、どの学部であっても不公平感があまりないとされています。
そのため「どの学部であっても、安定した設備供給が見込める」ということになるでしょう。